
世界三大宗教のひとつ「仏教」と日本古来の宗教である「神道」は、いずれも日本の宗教として根付いています。
しかし、一般的な日本人は、信仰している宗教を問われたら無宗教と答える人が多いでしょう。
果たして本当にそうなのでしょうか?
日本では、子供が生まれると神社でお宮参りや七五三のお祝いをします。結婚式も教会や神社で執り行う人が多いです。また、葬式は仏式で行う人が多いと思います。
このように、日本人は無意識のうちにいろんな宗教の行事や作法を取り入れているのです。特に、仏教と神道は日本に深く根付いています。
ところが、仏教と神道では行事の形式が異なるのをご存知でしょうか?
今回は、通夜と葬儀の形式の違いを説明していきましょう。
仏式の通夜

通夜は、葬儀前夜に夜通しで行う儀式です。
まず、一般的な仏式の通夜の形式を学びましょう。
どちらも夕方から数時間程度で済ませるのが一般的です。
故人の供養の一環として、会葬者にお酒や食事を振る舞うことを「通夜ぶるまい」と呼びます。
本来は精進料理を振る舞うのですが、最近はお寿司やお弁当、果物、お菓子などを用意することが多い。料理は、足りなくなることがあるので多めに用意しておくのがマナーです。
通夜ぶるまいには、通夜に訪れた人全員を誘います。しかし、遠慮する人などを無理に引き留めるのは避けること。
神式の通夜
 arget=”_blank”>通夜 – Wikipedia
arget=”_blank”>通夜 – Wikipedia
神道では死を「穢れ(けがれ)」としているため、通夜祭は神社ではなく自宅や斎場で行います。
と呼びます。
そして、通夜祭に引き続いて「遷霊祭(せんれいさい)」を行います。
故人の霊を遺体から霊璽(れいじ)に移す儀式。
「みたまうつし」とも呼び、仏式の位牌(いはい)にあたる霊璽に死者の例を移すための儀式です。
神道では、祭式の前に身を清めるために手水の儀(ちょうずのぎ)を行います。
手水の儀の作法は
- 桶の水をひしゃくですくう
- 左手を水で清める
- 右手水で清める
- 左手で水を受けて口をすすぐ
- その後にもう1度左手に水を注ぐ
- ひしゃくを元に戻す
遷霊祭では、玉串奉奠(たまぐしほうてん)という神事には欠かせない儀式も行います。
榊の木の枝に紙垂(しで)という奉書紙を細長く切って付けたものを玉串と呼び、それを神に捧げることを玉串奉奠といいます。
神道の基本は「二礼二拍手一礼」なのですが、通夜祭や葬儀祭の時は手を打つ祭に音を立ててはいけません!
「しのび手」といい、親指と親指をあわせるようにします。
通夜ぶるまいに関しては、神式も仏式とほとんど一緒です。
仏式の葬儀
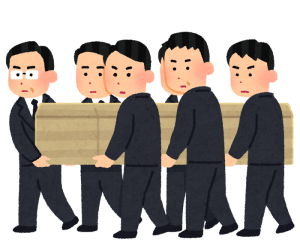
一般的な仏式の葬儀とは、故人の成仏と冥福を祈って僧侶が引導を渡す儀式です。
出席者も遺族と親族が中心となります。
告別式は、友人や知人など故人と縁のあった一般の人々が焼香によって最後のお別れをする儀式。
しかし、最近は葬儀と告別式が一緒に行われることが多いので、一般の弔問客も葬儀から訪れるのが普通になっています。
葬儀と告別式が一緒に行われる場合、葬儀は僧侶の読経に始まり、遺族や親族の焼香で終わります。その後、告別式に移り、一般の弔問客の焼香が済んだら終了です。
喪主や遺族は弔問客の送り迎えをせず、祭壇の前で弔問客の焼香と挨拶を受けるのが役目となります。弔問客の送り迎えは、近親者などに任せるのがマナーです。
神式の葬儀
神道では、仏式の葬儀や告別式にあたるものを「葬場祭と呼びます。
故人の霊は、祖先の霊とともに家に留まり一家を守る神になるとされています。
葬場祭は、死の穢れを清めて故人を神として祀るための儀式。
葬儀祭でも手水の儀や玉串奉奠を行います。
神道は、死を不浄なものとしているので、通夜祭と同様に葬場祭も神社ではなく自宅や斎場に神主を招いて行います。
準備の仕方は仏式とほとんど同じ。ですが、神式で行う場合は、慣れていない会葬者は多いので式次第や作法を記したものを配るなどの心遣いが必要になるでしょう。
最後に
服装は、仏式でも神式でも略式礼服で問題ありません!
仏式では焼香を、神式では玉串奉奠を行います。
数珠は、仏式で使うものなので、神式で持参するのはマナー違反です。
香典の表書きは異なります。
【仏式】
【神式】
日本人は、仏式の通夜や葬儀に慣れています。神式に参列する際は少しだけ注意が必要です。
行事の形式などをみても、宗教は私たちの生活に密接に関わっていることがわかるでしょう。




