
子供の運動能力の低下が嘆かれている昨今。
野球やサッカーを習っているにもかかわらず、運動神経があまりよくない子供をたくさん目撃してきました。
これは、コーディネーション能力の低下が原因といえるでしょう。
コーディネーション能力とは?

コーディネーションという言葉は、ファッション用語として使われているイメージが強いと思いませんか?
調整することで、インテリアやフード業界でも広く使われる。ファッションの場合,衣服やアクセサリーを一つのイメージで調和よくまとめて着こなすこと。ブラウス,スカート,靴,ハンドバッグなど、身に着けるもののすべて、あるいは一部を同一の色、素材、柄などで共通性、関連性を持たせ統一した全体的な美しさを強調する。
コーディネーションは、全体のバランスや調和などの意味を持つ言葉です。
スポーツの分野でのコーディネーションとは、自分の体を思い通りに動かす能力のこと。
コーディネーションの7つの能力
コーディネーションの能力は7つに分けられます。
リズム良く身体を動かす能力であり、目や耳からの情報を動きによって表現することを可能にする『マネッコ能力』でもあります。この能力はどんなスポーツにおいても欠かすことのできない基礎能力となります。
全身のバランスを空中局面などのいかなる場合においても保てることや、崩れた体勢を素早く立て直すことを可能にする能力です。リズム能力と同様にあらゆる運動の基礎となります。
引用:同上
条件に合った動作の素早い切り替えを可能にする能力。つまり、急に状況が変わり異なる動きをしなければならない時に、動作の素早い切り替えを可能にしてくれます。定位能力と反応能力と密接に関係があり、予測して先取りする能力でもあります。
引用:同上
合図に対して正確かつ素早く対応動作を可能にする能力です。これは、合図を聴覚からだけでなく、視覚や触覚や筋感覚からも含まれます。
引用:同上
関節や筋肉の動きを、タイミングよく無駄なく同調させることを可能にする能力です。力加減やスピード調整によって動きをスムーズにさせてくれます。
引用:同上
決められた場所や動いている味方・相手・ボールなどと距離感を関連付け、動きの変化を調節することを可能にする『空間把握能力』です。将来、アクロバティックな技術系や状況対応が求められるボールゲーム系の種目を目指すには欠かせない能力です。
引用:同上
手や足、頭部の動きを微調整する際の視覚との関係(ハンド・アイコーディネーション)を高め、ボールやハンドルなどの用具操作を精密に行うことを可能にする能力です。
引用:同上
これらを効果的に鍛えて、運動神経の発達を促すのがコーディネーショントレーニングです。
いわゆる運動音痴の人は、体の使い方を司るコーディネーション能力が欠けています。
幼児期までにコーディネーションを能力をトレーニングで鍛えれば、子供の運動音痴は防げます!
コーディネーショントレーニング
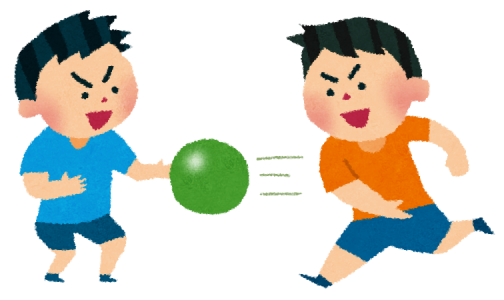
野球選手だから腕や肩を鍛えればいい、サッカー選手だから足を鍛えればいい、といったアプローチの仕方は過去の産物。
どのスポーツでも、全身をバランスよく鍛え、総合的な体の使い方を学ぶのが常識になっています。
そして、体を総合的に鍛えるのに導入されているのが、調整力を高めるコーディネーショントレーニングなのです。
コーディネーショントレーニングは、感覚神経を刺激して体の動かし方を学び、連動性を高めて、動き作りをするの。目的。
筋力強化を目的としたものではありません!
スキップやキャッチボール、鬼ごっこ、相撲、はしご状の器具でステップを踏むラダートレーニングなどがコーディネーショントレーニングに該当します。
子供たちには特定のスポーツだけでなく、さまざまなスポーツや遊びを経験させてあげる必要があるのです。
ゴールデンエイジまでに鍛えること

「運動神経がない」という言葉をよく耳にしますが、実は運動神経がない人はいません!
ちゃんと鍛えられていないだけです。
運動能力を司る脳の神経に刺激を与え、神経回路をつなぎ、しっかり鍛えれば運動神経は良くなります。
しかし、ゴールデンエイジ(9〜12歳)と呼ばれる時期を過ぎてしまうと改善は難しい…。
なぜなら、脳の神経系は
ところまで発達してしまうからです。
なので、コーディネーショントレーニングは幼い頃からしっかりやらなければなりません。
幼児期までに、いろんな遊びをしていれば運動音痴を防ぐのは簡単!
逆に、野球選手やサッカー選手を目指すのなら、即座の習得ができる12歳までにコーディネーショントレーニングでしっかり調整力を鍛えましょう。
【参考記事】幼児のサッカー指導は遊びながら楽しさを伝えることが大切。
最後に
コーディネーション能力は、あらゆるスポーツに欠かせません!
コーディネーションは、遊びに近い動作の組み合わせで鍛えられます。
脳の神経系が大人の90%に発達する6歳までに、さまざまなスポーツや遊びをやって運動音痴を防ぎましょう。





