
人間には、一日の周期でリズムを刻む「体内時計」が生まれつき備わっています。
体内時計の働きがあるからこそ、人間は意識をしなくても日中は活動状態、夜間は休息状態に切り替わるのです。
体内時計が狂うと、体中にあらゆる異変が起こります。なぜなら、それぞれの臓器が休息を求める時間が違うため。
そのため、リズムが少し狂うだけで体中に影響が及んでしまうのです。
各臓器の修復する時間帯と食事の関係

各臓器の修復する時間帯をみていきましょう。
【肺:3〜5時】
就寝中に肺は、空気と一緒に吸い込んでしまったほこりなどの小さな異物を処理しています。
塩分や添加物の多いものは、肺の負担になるので避けたほうがいい。
肺が正常な状態でないと、血圧や脈拍、体温に影響が出るので注意しましょう。
【大腸:5〜7時】
朝の健康習慣として、コップ1杯の水を飲むことが定着しているでしょう。
コップ1杯の水は、睡眠中に失われた水分を補うだけでなく、自律神経を目覚めさせる効果もあります。
また、大腸は朝の時間帯に体内の毒素を排出しようとします。その働きを水分補給が助けるのです。
【胃:7〜9時】
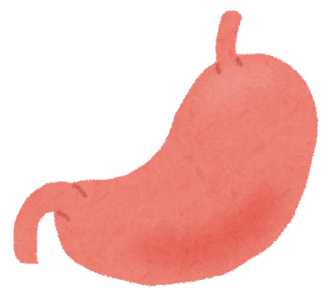
朝は、胃の働きが活発になる時間帯です。
朝食をとって、一日のエネルギーを蓄えるのに適しています。
【脾臓:9〜11時】
この時間帯は、脾臓がフルパワーで働きます。
脾臓は、血糖値をコントロールする臓器です。この時間帯に糖分が多いものは避けること。
また、この時間帯は胃が休みます。この時間帯に朝食をとると、胃に負担がかかるので注意しましょう。
【心臓:11〜13時】
ちょうど昼食をとる頃が心臓の休息と修復の時間帯にあたります。
心臓のメンテナンスができていないと、疲れを感じやすくなったり、機能が低下してしまいます。
なので、この時間帯にお腹がいっぱいになるまで食べるのは避けましょう。
食後は心臓に負担をかけないためにも、ゆっくり休ませたいところです。
【小腸:13〜15時】
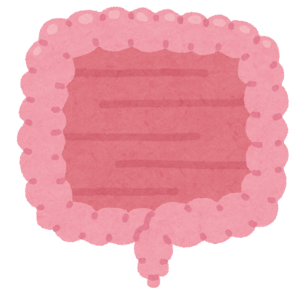
消化活動の中心となる小腸が体に休むように指示を出す時間帯。また、心臓が休息した後なので血液の循環も鈍くなっています。
午後になって、急激に眠たくなるのはそれが原因です。
そして、もし、この時間帯に消化不良や膨満感、痛みを感じるのであれば、何かの食べ物に対して体が過敏に反応している証拠。
食事の内容を見直す必要があります。
【腎臓と膀胱:15〜19時】
膀胱は、重要な解毒器官です。また、この時間帯に腎臓も活発的に働きます。
なので、15〜19時の間に水やお茶をたくさん飲むと、老廃物を排出するのに効果的。
この本来なら活力に溢れる時間帯に疲れを感じるのであれば、体質に合わない食べ物を摂りすぎているのかもしれません。
【膵臓:19〜21時】
膵臓は、血液内の糖分を作り出すインスリンを制御する働きをしています。
インスリンは、膵臓に存在するランゲルハンス島(膵島)のβ細胞から分泌されるペプチドホルモンの一種。
糖分の摂り過ぎなど食事に問題があると、糖尿病などの病気を引き起こします。
【動脈と静脈:21〜23時】
【肝臓と胆のう:23〜3時】
肝臓は、代謝機能や解毒作用、胆汁の生成といった重要な役割を担っています。
お酒を習慣的に飲む、脂っこい食事が多い、ストレス、不規則な生活などは肝臓を壊す原因です。
そして、睡眠に障害を抱えているのであれば、食事の内容に問題がある可能性あり。
この時間帯に寝つけないのなら、肝臓が体内の毒素を排除するために活発に働いていると考えられます。
【参考記事】グルテンを含む食品。謎の体調不良の原因は小麦粉にあった!
最後に
これで、体内時計を整えることがいかに重要であるか理解できたと思います。
食事をとる時間や内容が悪いと、体全体に悪影響を及ぼしてしまうのです。
各臓器が修復する時間帯を理解しておけば、体調不良の原因がどこにあるか理解できるでしょう。





