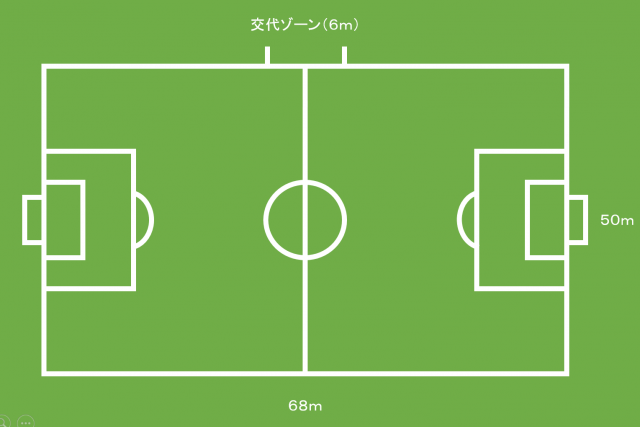ジュニア期に起こりやすいスポーツ障害。
スポーツ障害(スポーツしょうがい)は、スポーツ(運動)をすることで起こる障害や外傷などの総称である。
長期的に同じスポーツを続けることなどにより、体の一定の部位に負担がかかって起こる障害。スポーツにおける体の使い過ぎ(オーバーユーズ)を原因とするもので、成人だけでなく、成長期の子供にもよく起こる障害である。

指導者や保護者が身体の発育やケガに関する知識を身につけていれば、スポーツ障害は予防できます。
また、年齢に応じた効果的なトレーニングを行うことも可能です。
今回は、発育発達期におけるスポーツとの付き合い方についてまとめてみました。
発育発達の身体的特徴は?
男性は11歳、女子は10歳を境に急速な大人への成長をします。一般的にPHV年齢と呼びます。
身長の発育量に見合うだけの体重の増加は主に除脂肪体重の増加によるもの。
除脂肪体重(じょしぼうたいじゅう)とは、その個体の全重量から、その個体が持つ脂肪組織の重量を差し引いた、体重に関する指標の1つである。
除脂肪体重の定義を数式は、以下の通りである。
(除脂肪体重) (kg) = (体重)(kg) – (脂肪組織の重量)(kg)
それ以上の増加は脂肪量の増加による部分が大きいです。
体重は身長と似た発育パターンを示し、思春期発育スパート期に入って急激に増加します。
適度な運動負荷は骨密度が増し、骨の成長を促します。
しかし、過度な負荷は成長軟骨層に障害が生じやすい!疲労骨折が代表的なケガの例。
発育発達の心理的発特徴は?

【幼児期】
【児童期】
【思春期】
【青春期】
年齢を重ねるごとに心理的変化が現れます。
運動と成長の関係性

幼児期や児童期において運動と人格的発達は大いに関係があります。
スポーツや遊びを通じて「できた!」という小さな成功体験を積み重ねることで「自分はやればできる!」という自覚が芽生え、それが成長に役立つわけです。
また、基礎的運動パターンは6〜7歳までに習得します。
児童期の運動発達においては同じ動きの繰り返しよりも、さまざまな変化をつけた動きを経験するほうが学習効果は高くなります。
サッカーや野球など特定のスポーツのみを続けるよりも、鬼ごっこやドッジボールなどの遊びを取り入れたほうがトレーニング効果は高いです。
神経や筋肉の発達は?
発達の過程では、神経細胞やシナプス発達による神経回路の形成が盛んに行われます。
筋肉からの活動刺激によっても発達が促されるため運動は欠かせません!
運動感覚に関する深部感覚は10歳までに急速に発達します。
深部感覚は位置覚、運動覚、抵抗覚、重量覚により、体の各部分の位置、運動の状態、体に加わる抵抗、重量を感知する感覚である。深部知覚、深部覚、固有受容性感覚 proprioceptive sense、固有覚ともいわれる。これらの感覚の基礎として存在するのが関節、筋、腱の動きの感覚である。
さまざまな刺激の反応時間は6歳から12歳にかけて急速に短縮されます。
ジュニア期のスポーツでは、動作のイメージを大切にした動きづくりのトレーニング効果が大きいです!
【筋繊維】
収縮速度が速く、収縮力も大きいが疲労しやすい。PHV年齢以降に発達します。
収縮速度が遅く、収縮力の小さいので疲れにくい。幼児期、小学校期に発達します。
握力や背筋力は、男子と女子の筋力の発達がPHV年齢から大きく差がみられるようになります。
それは女性ホルモンの分泌による影響で速筋線維の発達が抑制されるからです。
そのため、指導者は性差を考えてトレーニングを考えなればなりません!
成長期の女子への配慮は必要不可欠。男子よりも発育発達の速度が早く始まることを頭に入れておきましょう。
発育発達期に多いケガや病気

発育発達期は、成長軟骨の存在していたり、成長のスピードにも個人差があるため、ケガを発生しやすいです。
など、スポーツ障害には十分に気をつけなければなりません!
また、怪我の原因も年齢によって大きく異なります。
【16歳未満】
- 転倒
- 受け損ない
- 衝突
【16歳以上】
- 衝突
- 転倒
- 着地
スポーツが原因で発生する病気もあります。
燃え尽き症候群(もえつきしょうこうぐん、英: Burnout)は、一定の生き方や関心に対して献身的に努力した人が期待した結果が得られなかった結果感じる徒労感または欲求不満。慢性的で絶え間ないストレスが持続すると、意欲を無くし、社会的に機能しなくなってしまう症状。
夏の熱中症対策、冬の寒さ対策は、ケガや病気を予防する上で大事なことです。
年齢に応じたトレーニング

年齢に応じて動きを吸収しやすい時期と吸収しにくい時期があります。指導者は、時期に適したトレーニングを実施しなければなりません!
特に、ジュニア期はスポーツの基礎をつくり、さまざま技術の習得において最も重要な年代です。
【プレ・ゴールデンエイジ(4〜8歳頃)の特徴】
【ゴールデンエイジ(9〜12歳頃)】
中学生になると、発育発達のスパート期を迎えます。
そして、高校生にもなれば、どんどん大人の体型に近づいていくので、フィジカルトレーニングの効果も大いに期待できるでしょう。
ただし、8〜15歳のうちは同じ年齢でも身体の発達に±3の個人差が生じるため、発育状態に応じたトレーニングを行う必要があることを忘れてはなりません。
最後に
身体の発育やケガの知識を身につけることにより、年齢に応じたトレーニングを行うことができます。
スポーツ障害の予防にもつながり、高いトレーニング効果も期待できるでしょう。
ジュニア期はスポーツの基礎をつくり、動きや技術の習得に最高の時期なので大事にしたいものです。