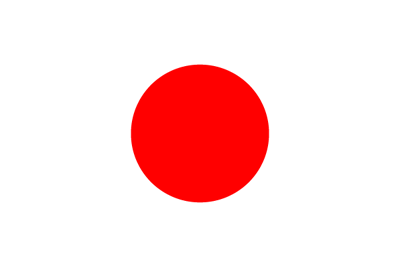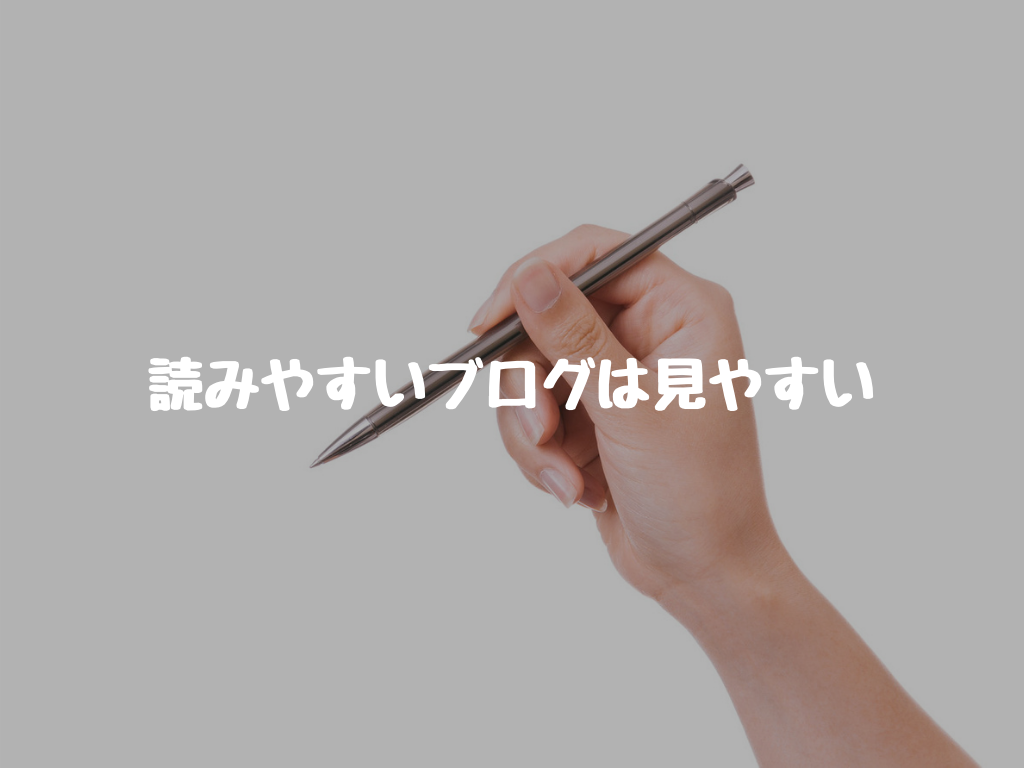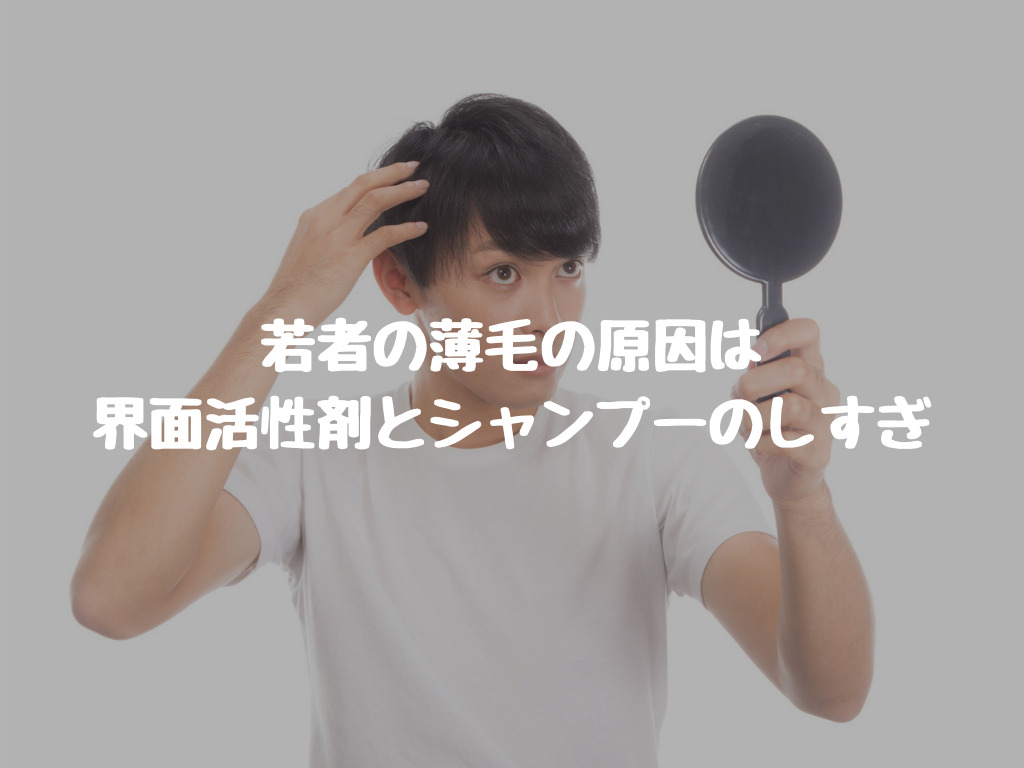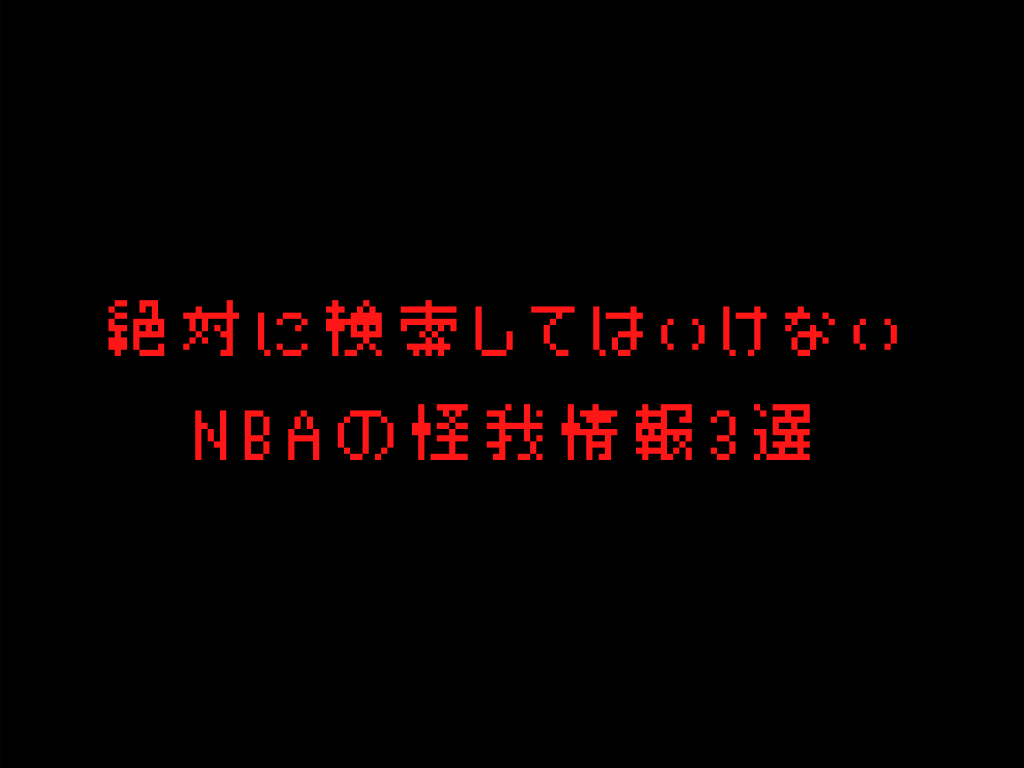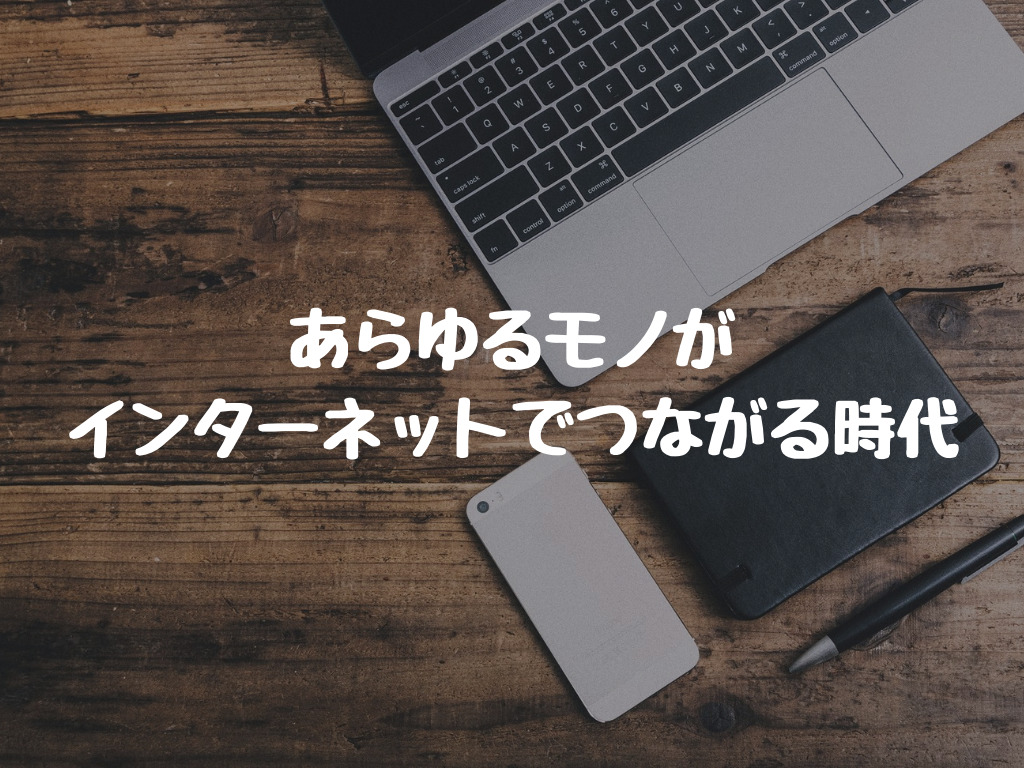
最近、自分より上の世代の人との対話を通じて感じたことがある。
それは、インターネットが生活文化にそこまで根づいていないということ。
メールやネットサーフィン、SNSなどをある程度、使いこなしている人が多いが、ネットショッピングや無料通話アプリ、クラウドサービスなどは完全に普及しているわけではない。
私は、デジタルネイティブ世代だ。小学生の頃から、当たり前のようにパソコンや携帯電話が存在していた。
例え、家庭にパソコンがなくても、パソコンの授業があったので誰しもがITに触れる機会が平等にあった。デジタルメディアやツールが身近にあったので、それらを自然に使いこなすのが当たり前。
しかし、自分より上の世代は少し事情が異なる。
私は、世の中の大多数の人がAmazonや楽天市場などのネットショッピングを日常的に利用していると思っていたけど、実際は過半数にも満たないという印象だ。
利用していない理由を聞くと、パソコンを下手にいじくるとウイルスに感染するのではないか、クレジットカードの情報を抜き取られるのではないか、と答える人が非常に多い。
パソコンやインターネットに対して、抵抗感や拒絶反応があるのだ。私は、ちょっとしたカルチャーショックを受けた。
パソコンにウイルス対策ソフトをインストールしておけば、簡単にウイルスに感染することはないし、大手ネットショップで普通に買い物をするだけならクレジットカード情報を抜き取られることはない。
もはや人は情報なしには生きていけないという時代が始まっている。
高度な情報活用なしに、高度な社会生活を送れない時代が来ているのだ。にもかかわらず、インターネットがあまりにも生活文化に馴染んでいない。これは大きな問題だ。
パソコンやインターネットをうまく利用すれば、無駄な時間を使うことなく快適に仕事を進められたり、ちょっとした時間でお金を稼げたりと、効率よく生活を送ることができる。
マスコミは「インターネットは誹謗中傷ばかり」「パソコンやインターネットを使えない人はどうするのか」というITに関してどうでもいいネガティブな情報ばかりを流す。
ITを使いこなせない人がいることも問題だけれども、それ以上に「使いこなせる人をどうしたらもっと増やせるのか」という議論を何故しないのだろうか?
そもそも、使えない人のレベルに合わせようという発想自体が間違っている。
あらゆるモノがインターネットでつながる時代だからこそ、一人でも多くの人の生活文化にインターネットを浸透させていく必要があるのだ。
最近、パソコンやインターネットに対する誤解、利便性、活用法などについて説明する中で改めてこのようなことを感じている。
そして、自分の中で当たり前のことは、全然当たり前のことではないということを再確認できた。
やはり、リアルなコミュニケーションで学ぶことは重要である。